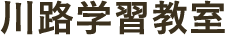人類学について引用して考える『ひっくり返す人類学』生きづらさの「そもそも」を問う 奥野克巳 著
- お知らせ
もう一つのホームページでブログを書いた。今のところ、3回分を引用して、考えてみたが、まだまだ終わらない。ここでも、その人類学について考える。その著書は、『ひっくり返す人類学』生きづらさの「そもそも」を問う 奥野克巳 著を取り上げる。
一回目は、
『ひっくり返す人類学』 生きづらさの「そもそも」を問う 奥野克巳 著 ちくまプリマー新書 より引用。
「 次に紹介するのは、アフリカのボツワナ北部のクン・サン(ブッシュマン)の調査において、カナダの人類学者リチャード・リーが経験したある出来事です。彼は、一年以上にわたって実施したフィールドワークのお礼として、牛を一頭屠畜(とちく)してクリスマス・プレゼントにしようと考えました。
しかし驚いたことに、クン・サンの人たちはリーの前でその大きな牛を見て、老いぼれだの瘦せっぽっちだと口々に悪口を言ったのでした。そのことにリーはショックを受けます。ところが、宴会当日になってみると、牛は肉づきがよくてやわらかく、料理は人々にとってとても満足のいくものだったようなのでした。
リーは、彼らの牛に対する悪口は、大きな牛を贈ったリー自身の尊大な気持ちに対するものだったのではないかと言います。いったいどういうことでしょうか?リーは、クン・サンの人たちのいつもの狩猟行動を振り返っています。
クン・サンの狩猟者は、弓矢猟に出かけ毒矢を命中させると、いったんキャンプに戻ります。その後、仲間とともに獲物追跡と運搬のためにふたたび出かけるのです。出かけた先で獲物をうまく仕留めると、仲間たちは、「自分たちをこんな骨ばかりのものを運ばせるために連れ出したのか」と獲物に対して悪口を言い始めます。
しかし、そうした悪口はその場だけのことで、キャンプに運び込まれた獲物はみなで満足して賞味されるのです。それでは、獲物に対する悪口とは、いったい何のためだったのでしょうか?それは、狩猟者が、自分が獲った獲物の大きさに天狗になって他の人たちに自慢したり、威張ったりすることを牽制(けんせい)するためだったと、リーは解釈しています。
ちくまプリマー新書の『悪口ってなんだろう』の著者である和泉悠によれば、クン・サンは悪口を言うことによって、誰かが調子に乗るのを防ぎ、大物、すなわち権力者が生まれるのをあらかじめ防ごうとするのです。そうした振る舞いは、平等主義的な狩猟採集民の社会において幅広く観察されています。悪口は、権力者が生まれるのをあらかじめ防ぐために用いられていたのです。
でも、そのようにクン・サン自身が言ったのではありません。それは、あくまでも人類学者リーの推察です。しかし本人たちが述べていなかったにせよ、それを権力を発生させたり権力を特定の誰かに持たせたりすることがないように、無意識のうちに、集団的に工夫されたひとつのやり方なのかもしれないと考えるのは妥当なことでしょう。ここでも、人類による工夫、特に権力を否定して、誰もが平等に暮らしていくための工夫が狩猟採集民社会においてなされてきた片鱗を見ることができます。
人類はこれまで、権力が集中したり、権力の発生を未然に防いだりするやり方をすでに自前で持っていたのです。そして、地球上にはいまだに、それらのことをいとも簡単にやってのける人たちがいるのです。
逆に言えば、権力から逃れることのできない私たち現代人は、人類として、とてつもなく遠いところに来てしまっているのかもしれません。振り返れば、格差を「そもそも作らない」世界を目指した上で、権力が集中しないような工夫をすることが、現代世界において根本的な解決の見通しが立てられない経済格差と権力の問題を解きほぐすためのひとつの大きな糸口になりうるのではないでしょうか?」
二回目は、
『ひっくり返す人類学』 生きづらさの「そもそも」を問う 奥野克巳 著 ちくまプリマー新書 より引用 前回の 今週の一言 第二十九回で『ひっくり返す人類学』の題名のもとになった「ひっくり返す」とはどういう意味なのかを本書より引用し、紹介したい。そもそも人類学とはどのように始まったのか。
「国家間の戦争というのはいつの時代にもあります。今から100年以上前にもヨーロッパで大規模な戦争がありました。1914年から1918年にかけては、ドイツ、オーストリア、オスマン帝国などと、イギリス、フランス、ロシアなどのあいだで、第一次世界大戦が勃発し、850万人のヨーロッパ人の命が奪われたとされます。
フランスの詩人ポール・ヴァレリーが評論「精神の危機」の中で、ヨーロッパは戦争を止めることができなかったし、ヨーロッパ人が築き上げてきた知は無力であると唱えたのもこの時代です。世界の中心のようにふるまい、様々な富や知識を蓄えてきたヨーロッパ諸国でしたが、大規模な戦争によって人々は精神的・物質的な危機に陥り、生きづらさを感じ始めたのです。
そしてちょうどその頃、ヨーロッパ内部に閉じているだけでは不十分であると考え、ヨーロッパ以外の世界に赴いて、そこで暮らしながら人間の生き方を探ろうとしたのが、本書が基盤とする人類学でした。人類学という学問は、戦争という負の歴史とともに発展してきました。」
このあと、なぜ「ひっくり返す」人類学なのかが次第に分かってくる。それはまた次回に続く。
そして、3回目は、
『ひっくり返す人類学』生きづらさの「そもそも」を問う 奥野克巳 著 ちくまプリマー新書 より引用
「ブナンとは、ボルネオ島に住む狩猟採集民および狩猟採集民に与えられた民族の総称です。今もなお狩猟採集だけに頼って暮らしている人たちがいるということに、私は大いに興味をそそられたのでした。農耕以前の段階の。人類の古い生業である狩猟採集を参与観察して、人々の暮らしを見てみたいと思うようになったのです。そこに、人間の原初の暮らしがあるのではないかと想像したのです。
その後、2000年代の半ばに、当時勤めていた大学から研究休暇をもらって、1年間にわたってブナンのフィールドワークを実施することにしました。くわしいことはのちのちお話ししていきますが、その後も2024年の春に至るまで、コロナ禍の2年半の中断を挟んで、年2回ずつ、2週間から一ヶ月ほどのフィールドワークを繰り返してきています。2024年で、フィールドワークを始めてから19年目になります。
フィールドワークでは、狩猟について行って森の中を歩き回り、夜中には地べたに寝たりもしました。時には道に迷ったこともあります。ブナンのハンターたちがヒゲイノシシやシカやサルなどの獲物を捕まえて、狩猟キャンプにそれらを持ち帰り、共同体の中で肉を分配するまでの詳細を記述し、分析しました。狩猟に出かけていないあいだにも、神話や民話、人々の日常の語りに耳を傾けて、狩猟採集民ブナンの考えややり方を探ったのです。
でも最近ではフィールドワークに行ってもほとんどノートは取りません。小屋で寝っ転がって人々の話を聞いているほうが、一生懸命にノートや録音をとるよりも、ブナンの考えていることや、やっていることがよく理解できるように思えるからです。フィールドワークの手法も、長くやっていると変わっていくものなのです。」
ここからが主題である『ひっくり返す人類学』とは何か?に話しが展開されていく。次回 今週の一言 第三十二回 へと続く。引用はまだまだ終わらない。